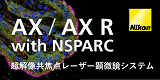2024年度塚原仲晃記念賞受賞者 杉山(矢崎) 陽子 先生 受賞の言葉
沖縄科学技術大学院大学
杉山(矢崎) 陽子
杉山(矢崎) 陽子
この度は私達のキンカチョウを用いた発達期の発声学習の神経メカニズムの研究について、塚原仲晃記念賞受賞の栄誉を賜り、大変光栄に存じます。これまでご指導下さった先生方、共同研究者の皆さん、そして研究室の皆に感謝申し上げます。
私の研究は、大学(日本女子大学)の「神経行動学」の授業で動物の特徴的な行動を司る神経回路の仕組みを知る、という学問に興味を持ち、上智大学の青木清先生の研究室に外研生として入ったことからスタートします。そのまま上智大学の大学院に進みました。青木先生は「自分の好きな研究をしなさい」という方で、研究者として一番大切な独立性と独自性を教わりました。青木研究室では、助手でいらした松島俊哉先生(後に名古屋大学、北海道大学)のご指導でウズラの発声神経中枢がヒナと成鳥で異なる発声パターンを作り出すことを見出し、神経可塑性の面白さに出会いました。また、研究室を青木先生の親友のカルフォルニア工科大学のMark Konishiが時々訪ねて来ました。Konishi先生はソングバードやメンフクロウの仕事を立ち上げた高名な先生でありながら、気さくで温かい人で、色々な助言を頂きました。ポスドク先についてもKonishi先生に相談し、お弟子さんでもあるDuke大学のRich Mooney教授を紹介して頂きました。
日米脳の助成金も頂き、Mooneyラボに飛び立つ直前、大学時代の友人達が開いてくれた送別会中にテレビで飛行機がビルに突っ込むのを見ました。その様な混乱の中スタートしたポスドク生活でしたが、Mooneyラボではキンカチョウ脳内のLMANという領域の神経細胞が学習によって変化する自身の歌に常に聴覚応答することを明らかにしました(Yazaki-Sugiyama & Mooney, 2003)。この研究を通して生体内細胞内記録の技術を教わりました。私はMooneyラボの初のアジア人、唯一のnon-native English speakerでしたが、Richもラボメンバーも親切で仲が良く、研究のこと、キャリアのこと、様々なことを話し、多くを学びました。この時のポスドク仲間は未だに大事な友人です。日本に帰るに当たり、Richから「ポスドクの時に一度は競争の激しいフィールドに行き、どの様に生き抜くのか学べ」とアドバイスを受けました。そこで帰国後は理化学研究所脳科学研究センターのTakao Hensch先生の研究室にお世話になることになりました。
Henschラボではマウスを使って眼優位可塑性の研究をしていました。私には細胞内記録の技術を立ち上げて欲しい、その技術で何をやってもいい、と言われました。そこで細胞内記録を立ち上げ、細胞の動態を見ていると「第一次視覚野で見られる優位性はどこで出来ているのか」という根本的な疑問を抱きました。一つの神経細胞で、入力と出力を同時に見られる細胞内記録法を使って解くには最適の疑問でした。この研究を進める過程で偶然取れた、たった数個の抑制性神経細胞のデータを見て、Hensch先生が「これは逆の可塑性を示している様に見える。これを徹底的に見よう」と言い出しました。小さな抑制性細胞から記録するのは無謀にも聞こえましたが、性質を探りながら細胞に向き合うのは楽しく、抑制性神経細胞のAnti-Hebbian plasticityを発見することが出来ました(Yazaki-Sugiyama et al, 2009)。またこの間の2005年と2008年に長男、長女を出産しましたが、Hensch先生は応援、サポートして下さいました。色々な人に支えられ、楽しく子育てと研究を行い、長男が成人した今年、塚原賞を頂くことになり感慨深いです。Henschラボでの仕事が纏まり始めたころから、Hensch先生と独立する話をするようになりました。自分は生物学の研究がしたいと思い、ソングバードの研究は面白い生物学的疑問があるにも関わらず、聴覚学習の神経回路メカニズム、臨界期のメカニズムの研究が殆どないことに気づきました。大学院開学に向けて教員を募集していたOISTにこの様な研究をしたい、と応募したところ、Assistant Profのポジションを頂きました。
私が赴任した当時のOISTは教員がまだ30名程度しかおらず、皆で新しい大学院を作る、という気概にあふれていました。一方でOISTはアメリカのようなTenure track systemを採用していて、5年半後にTenure審査を受けるという大きなプレッシャーがありました。そこで最初は既にある電気生理の技術を用い、学習中に脳のどの領域で神経可塑性が起きるのか、という根本的な疑問を解き明かすことに専念しました。そしてキンカチョウヒナが親の歌を聴くことで高次聴覚領域に歌の聴覚記憶が出来ること(Yanagihara & Yazaki-Sugiyama, 2016)、一次聴覚野では生得的に歌のテンポに反応し、これを用いて自身の種の歌を聴き分けていること(Araki et al, 2016)を明らかにしました。またOISTでは毎年、Davie Van Vactor教授(Harvard大学)と一緒にワークショップ(DNC)をオーガナイズさせて貰いました。このDNC講師たちとの繋がりが出来ることで、国際的なコミュニティーに入っていくことが出来ました。Tenure審査についても日本では採用されていないため、DNC講師やHensch先生から多くの助言を受けました。お陰様で2017年に無事にテニュアを頂きました。また電気生理実験に私達が集中する間、2013年に着任してくれた諸橋雄一博士がソングバードにウィルスベクターを最適化するという仕事を背負ってくれました。お陰で、近年ではこの手法を用いて神経細胞をターゲットして記録したり(Kudo et al, 2020, Spoor et al., 2021)、オプトジェネティクスなどの技術を取り入れることも可能になり、社会的音声コミュニケーションによる学習メカニズムなど(Katic et al., 2022)新たな方向へ研究が発展しています。
また2018年から5年半ほど、Hensch先生が機構長として率いる東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構でも研究をさせて頂き、聴覚記憶細胞が歌学習期にのみ運動野に投射する、という脳内領域間の神経回路編成を見出しました(Louder et al.2024)。
また2018年から5年半ほど、Hensch先生が機構長として率いる東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構でも研究をさせて頂き、聴覚記憶細胞が歌学習期にのみ運動野に投射する、という脳内領域間の神経回路編成を見出しました(Louder et al.2024)。
こうしてこれまでの研究を振り返ると、波乱万丈の中、常に先生方、研究仲間に支えられ、彼らとのコミュニケーションの中でサイエンスが作られていることが分ります。私達の研究室の研究テーマはLearning to communicateですが、やっていることはLearning from communicatingです。これまで私のサイエンスに関わって下さった全ての方に感謝を申し上げます。また、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻頂ければ幸いです。この度はどうもありがとうございました。

杉山(矢崎) 陽子
沖縄科学技術大学院大学
【略歴】
| 1999年 | 博士号(理学)取得 (上智大学) |
| 1999年 | 上智大学 生命科学研究所 博士研究員 |
| 2001年 | Duke大学 博士研究員 |
| 2003年 | 理化学研究所 脳科学総合研究センター 博士研究員 |
| 2011-年 | 沖縄科学技術大学院大学 准教授 |
| 2017年 | 沖縄科学技術大学院大学 准教授 (Tenured) |
| 2023年 | 沖縄科学技術大学院大学 教授 |