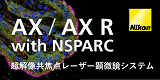2025年度時実利彦記念賞受賞者 伊佐 正 先生 受賞の言葉
京都大学大学院医学研究科
自然科学研究機構生理学研究所
伊佐 正
自然科学研究機構生理学研究所
伊佐 正
この度、日本神経科学学会の学会賞である時実利彦記念賞を戴けることになり、時実先生が開設された研究室(東京大学医学部付属脳研究施設脳生理学部門)で大学院と助手時代を過ごした者として、格別の思いを感じています。
私は大学の医学部の学生時代に、たまたま生理学の実験に触れて虜になり、それをより詳しく学びたいと思って大学院に入りました。大学院、スウェーデンへの留学、そして帰国しての助手時代は、1950-70年代にスタンダートであったネコを実験対象として脳幹や脊髄による運動制御機構を古典的な電気生理学や神経解剖学や破壊実験を用いて解析する研究を行っていました。ところが当時の1980-90年代は分子神経生物学、サルを用いた高次脳機能研究、ヒトの非侵襲脳機能イメージング、計算論的神経科学という新しい研究パラダイムがほぼ同時に爆発的に発展した時代で、私も自分の領域を広げる必要があると感じて、群馬大学に異動させていただき、グルタミン酸受容体の分子生理学研究に転じました。しかし当時これは最も競争の激しい分野の一つで、欧米のトップラボとの競争に悪戦苦闘していました。
そのような時に、生理学研究所において自分の研究室を立ちあげるチャンスをいただきました。当時の生理学研究所の先生方は「今は分子生物学全盛だが、いずれ分子生物学を使って脳のシステムを解明する時代が来る」と考え、私に白羽の矢が立ったとのことでした。その時、私にはどうすれば分子生物学を使って脳のシステムを解明すればよいのか明確なアイデアはありませんでしたが、その後、予想を超えて時計の針は速く回り、光遺伝学、化学遺伝学の時代が到来し、サルで経路選択的に機能操作を行う手法を開発し、感覚運動系の特定回路の正常機能と脳・脊髄損傷後の機能回復への寄与を明らかにすることができました。その後、9年前に京都大学医学研究科に異動し、連携の輪が広がって、より高次な意思決定や精神神経疾患モデル霊長類の研究に展開することができました。このように、まさしく「分子生物学を用いて脳のシステムを霊長類で解明する」研究分野をリードすることができました。
具体的には、霊長類の手の巧緻運動は、運動野由来の皮質脊髄路から手指筋運動ニューロンへの直接経路が必須と考えられてきましたが、私たちは、サルにおいても、皮質脊髄路から中部頚髄の脊髄固有ニューロン(PNs)を介する間接経路が存在すること、さらに頚髄で皮質脊髄路を完全に遮断しても、数週間で手指の巧緻運動がほぼ完全に回復することを示しました。そしてこの機能回復にPNsが関与することを証明するために、PNsを選択的に遮断する手法を開発しました。この方法では、神経路を逆行性に運ばれるウイルスベクターを投射先の神経核に注入、そして第二のウイルスベクターを細胞体の部位に投与し、二重感染を起こした神経細胞のシナプス伝達を可逆的に止めることを可能にしました。このようなintersectionalな経路選択的遮断法は、今では多くの研究者が使っていますが、当時はまだマウスの研究者すらも使っていなかったものを霊長類において最初に開発したという独自性がありました。そしてこの手法を用いて、PNsを介する間接経路が皮質脊髄路切断後の巧緻運動の回復に関わることを明らかにしました。一方で、陽電子断層撮影法(PET)を用いた非侵襲的脳機能イメージングにより、この機能回復過程において、回復初期は損傷同側の運動野、その後安定期では運動前野が機能回復に寄与するなど、通常は使われていない脳部位が順次動員されることを明らかにし、さらにこの「損傷同側運動皮質の活性化」には、「損傷反対側の運動野」からの入力が重要であることを大規模データ解析による数理科学的手法を用いて提案し、ウイルスベクター2重感染法にDREADDs法を組み合わせて脳梁を介する半球間経路が関わることを明らかにしました。さらにより上位のレベルでは、モチベーションの制御中枢とされる側坐核が回復初期に運動野を活性化することで機能回復を促進することも明らかにしました。それまで、脊髄損傷からの回復に関する研究は、主としてげっ歯類を用いた「損傷された脊髄を再度繋げる」研究が主流でしたが、私達は、機能回復を運動学習の一過程ととらえ、損傷を免れた神経システムが脳全体で機能を代償するというパラダイムシフトを起こすことができました。
また、ヒトにおいて一次視覚野に損傷を受けた患者の一部において、障害視野の視覚対象に対して「意識的にのぼる気付き」はないが、それに眼を向ける、腕を正確に伸ばすことができるという「視覚的意識と運動の乖離」を示す事例が存在します。この現象は、盲視(blindsight)と呼ばれ、議論の的となってきました。私達は、一次視覚野を損傷したサルを用いて、進化的に古い視覚系である網膜から中脳の上丘と視床枕を介して高次視覚野・頭頂連合野に至る経路と、網膜から外側膝状体を介して直接高次視覚野・頭頂連合野に至る経路の両方が一次視覚野損傷後の視覚認知行動を可能にしていることをウイルスベクター2重感染法による回路操作、PETによる非侵襲脳機能イメージング、そして薬理学的機能阻害法などを駆使して明らかにしました。一方で、この盲視の状態でも、「何かがある気がする」という意識経験が残っていること、短期記憶が可能であること、視野内のサリエントな刺激に自然に視線を向けること、そして行動と報酬を結びつける連合学習が可能であることなど、多くの視覚認知機能が残存していることを明らかにすることができました。
そしてより近年は、柔軟な意思決定における中脳ドパミン系の機能を調べています。特に高リスク高リターン(HH)か低リスク低リターン(LL)かという意思決定に関して、腹側被蓋野(VTA)のドパミン細胞にウイルスベクターを用いて赤色光によって神経細胞を興奮させる膜タンパクChrimsonRを発現させ、VTAから前頭葉の6野腹側部の6VV野への経路に赤色光を当てて選択的に活性化したところ、HH嗜好性が増強しました。それに対し、やや背側の6VD野への経路を活性化したところ、HH嗜好性が低下しました。さらに、この刺激を繰り返していると効果が蓄積し、6VV野への経路の刺激継続によってHH嗜好性が慢性的に増強され、6VD野への経路の刺激継続によってはよりHH嗜好性は低いレベルに維持されました。以上の結果により、意思決定のリスク嗜好性が中脳から前頭葉6V野のサブ領域に投射するドパミン作動性経路の活性化のバランスによって決定され、いずれかの経路に強い刺激が加わり続けるとサルの意思決定様式が慢性的に変化してしまうことが明らかになりました。このような知見はギャンブル障害などの依存症のメカニズムの理解と治療につながる可能性があります。これらの研究は現時点において、世界中のどの研究グループよりも洗練された方法で光遺伝学を用いて霊長類の前頭葉に至る特定経路を操作して高次な認知機能への関与を因果的に示したものと考えています。
今後、これらの手法を精神神経疾患のモデル霊長類に使用して、病態メカニズムの解明と治療法の開発につなげていきたいと考えています。

伊佐 正
京都大学大学院医学研究科(教授/医学研究科長・医学部長)
自然科学研究機構生理学研究所(所長)
自然科学研究機構生理学研究所(所長)
【略歴】
| 1985年 | 東京大学医学部医学科卒業、医師免許取得 |
| 1989年 | 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、医学博士取得 |
| 1988-90年 | スウェーデン・イェテボリ大学・客員研究員 |
| 1989-93年 | 東京大学医学部付属脳研究施設・助手 |
| 1993-95年 | 群馬大学医学部・講師 |
| 1995年 | 同・助教授 |
| 1996-2004年 | 岡崎国立共同研究機構生理学研究所・教授 |
| 2004-15年 | (改組により)自然科学研究機構生理学研究所・教授 |
| 2015年-現在 | 京都大学大学院医学研究科・教授 |
| 2022年-現在 | 京都大学大学院医学研究科長・医学部長 |
| 2025年-現在 | 自然科学研究機構生理学研究所・所長 |